| 2月の相談日 | 7日(土) 15日(日) 25日(水) |
|---|---|
| 3月の相談日 | 7日(土) 15日(日) 27日(金) |
茨城県ひたちなか市で相続についてお悩みは「来栖会計事務所」へご相談下さい
 平日 9:00~17:00
平日 9:00~17:00
 平日 9:00~17:00
平日 9:00~17:00
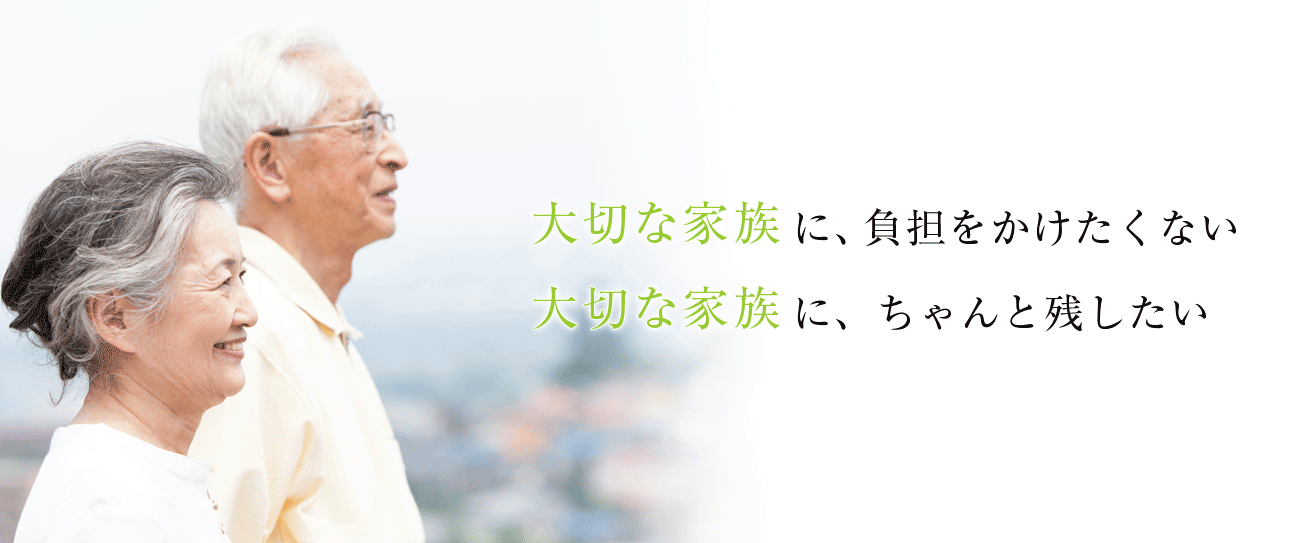

| 2月の相談日 | 7日(土) 15日(日) 25日(水) |
|---|---|
| 3月の相談日 | 7日(土) 15日(日) 27日(金) |

令和3年の7月から、認知症や亡くなった人がどういう生命保険に加入していたかを、一括して問い合わせが出来るという「生命保険契約紹介制度」が始まります。生命保険協会のホームページの照会画面から申し込む方法...


相続時精算課税は、生前に累計額2500万円までの金額を贈与税無しで、相続人に贈与する方法なのですが、これを一度使うと、同じ贈与者からは1年ごとに計算する暦年課税は使えなくなります。(ただし、相続時精算...


税理士が相続に詳しいかどうかを判定する一つの方法は、相続税法の最新の改正内容を自分である程度調べておき、そのことについて税理士に質問してみることです。コンスタントに相続を取り扱っている税理士であれば、税法の変更点は押さえているはずなのでスムーズに答えてくれるでしょう。税理士選びで最も重視したいのが、節税に真正面から取り組んでくれるかどうかという点です。例えば、相続財産にかかる税率が40%の場合、財産の評価額が200万円下がるだけで支払う税金は80万円も下がります。つまり、財産評価の仕方一つで、節税できる金額が大きく変わってくるわけです。


何年かぶりに研修を受けて、「相続アドバイザー」という資格を取りました。相続税の申告については自信があるのですが、 事前対策、贈与、相続人同士の分割、など多岐にわたります。今までよりは、相続に対して幅広い目で対応していける かなと思っています。
続きを読む相続の放棄をするのには、相続を知った日から3カ月以内に裁判所で、放棄の手続きをします。 遺産分割をするときに遺産を取得しなくても、それは放棄にならず、単に受取らなかったと いうだけで、放棄にはなりません。被相続人の持つ負債が財産より多い場合、放棄の手続き をしないでおくと、負債の方も継承してしまいますので、注意が必要です。なお、死亡保険金 の受取人に指定されていれば、放棄しても受け取ることはできま...
続きを読む2024年(令和6年)3月1日、最寄りの市区町村役場において、ほかの市区町村役場の戸籍謄本であっても、一括して取得することができる制度が始まりました。戸籍を管轄する法務省の戸籍情報連携システムを利用した仕組みで、これを「広域交付制度」と言います。 広域交付制度を利用して取得できる戸籍謄本の種類と手数料は以下のとおりです。 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):1通450円 一般に「戸籍謄本」とは、戸籍...
続きを読む従来、分譲マンションの評価は、マンション1室の固定資産税評価額と敷地権割合額の合計で決められていましたが、戸数が多く高層階ほど、時価が高くなるタワーマンションでは、売買価額との開きが大きくタワーマンションを買って節税する、いわゆる「タワマン節税」が横行していました。そのため、市場価額の6割以下の場合、その水準まで評価が引き上げられることになりました。この改正は令和6年1月1日以後の相続、贈与から適...
続きを読む来年から、贈与税の死亡前の加算が3年から7年に変わります。 令和6年1月1日の贈与から適用になるので、実際は3年後の時点 までは3年前の遡りは変わらないのですが、4年を過ぎると令和 6年以降の贈与加算が1年ずつ延びていき、結局令和6年の贈与は 7年過ぎないと加算から切り離されないことになっています。 贈与するならば、今月の贈与をお薦めします。
続きを読む